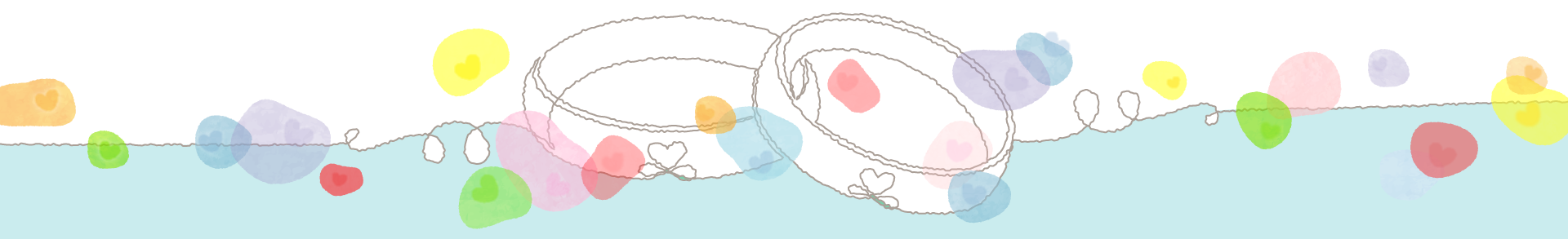
家族のかたち
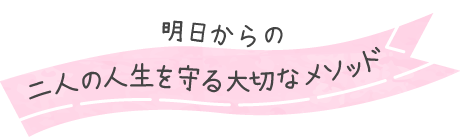
パートナーシップ契約
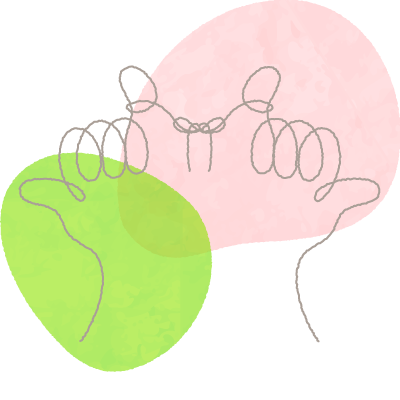
いま、パートナーシップ制度の活用が全国規模で広がっています。
「パートナーシップ制度」とは
婚姻していないカップルに一定の法的保障を与える制度です。
2025年1月1日時点で、パートナーシップ制度の日本の総人口カバー率は90%を超えました。(参照:公益社団法人MarriageForAllJapan)
千葉市では同性異性問わず、「パートナーシップ宣誓証明書」及び「パートナーシップ宣誓証明カード」が交付されます。
また、宣誓を受けることにより、市営住宅の申し込みや千葉市から弔慰金が受け取れるなどのメリットがあります。
しかし、全ての自治体で定めているとは限らず法的保護も十分ではないため、宣誓を証明しただけでは何かが起きた時に守られません。
渋谷区のパートナー証明書の発行には「合意契約公正証書(パートナーシップ契約書)」と「任意後見契約」2つの締結が条件になっています。
今後安心して暮らしていくためにも、ぜひこの機会にパートナーシップ契約のことをご一緒に考えてみませんか?
公的に保護される二人の未来 〜 パートナーシップ契約の結びかた
婚姻契約公正証書とは?
現在の日本では、民法上の婚姻は異性カップルにおいてのみ認められており、婚姻制度を(戸籍上の)同性カップルが利用することはできません。
婚姻契約公正証書を結ぶことで婚姻に近い権利義務を発生させることが可能になります。
同性カップルや異性の事実婚カップルが自分達の関係を守る為に私的な契約を結び、公正証書で契約書を作成します。
婚姻制度と同じような効果をお二人の契約という形で実現できます。また、婚姻生活上のルールはもちろん、医療代理権や亡くなった後の手続きのこと(死後事務委任)も記載できます。
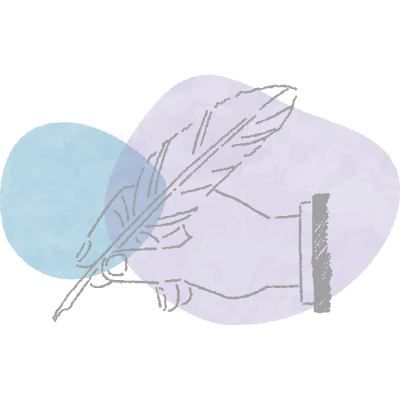
パートナーシップ契約のメリット(例)
- 結婚新生活支援事業補助金の交付申請
- 病院での付添いや手術の同意などで家族に近い扱いが得られやすい
- 市営住宅などへ家族として入居が可能
- 市営霊園の申し込み
- 生命保険などの受取人指定が可能
- ファミリーシップ制度(千葉市)※1の公的サービスを受けられる
※1 パートナーシップ宣誓者に未成年の実子または養子がいる場合、証明書や証明カードに記載が可能。また、15歳以上の場合は実子または養子の同意が必要です。
デメリット(例)
- 自治体ごとに許容できる権利が限られている
- 外国人パートナーに居住、労働ビザを提供できない
- 事務手数料などが発生する
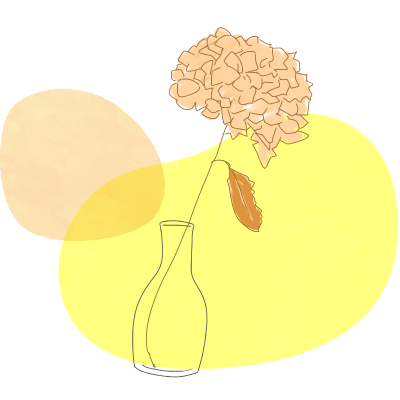
エンディング後もパートナーをサポートする様々な仕組み
大切な財産や日常生活を守るために
-
任意後見契約
認知症等になり、自分の意思を伝えたり判断できなくなった時に備えて、あらかじめお互いをそれぞれの後見人として選任する契約書を結び公正証書で作成します。似たような制度で法定後見制度もございますが、こちらはパートナーが後見人に指定されるとは限りません。 -
遺言公正証書
パートナーが亡くなった場合、遺されたパートナーには相続権が無いため、財産は亡くなった人の法定相続人が相続します。しかし、遺言公正証書を作成していれば、パートナーに財産を残すことができます。ただし、あくまでも遺贈という相続になるので、相続税や遺留分の問題を考慮して作成しましょう。また、法定相続人との争いを避けるため公正証書での作成をおすすめします。 -
養子縁組
届出書を市役所に提出し、養子縁組を結び親子関係による家族になることも可能です。ただし、年上の方が必ず「親」になり、「子」は「親」の戸籍に入る必要があります。養子縁組を結んでいると、自治体のパートナーシップ制度を使用できなくなるデメリットもあります。一度、養子縁組を結んでしまうと、将来法律が変わり同性での婚姻が認められたとしても婚姻することができなくなってしまうので注意が必要です。
千葉市パートナーシップ宣誓制度について
-
宣誓事項
- 2者が同等の権利を有し、相互の協力により維持される関係であること
- 同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、必要な費用を分担すること
-
宣誓要件
- 成年であること
- 市内在住又は市内への転入を予定していること(いずれか一方で可)
- 配偶者がいないこと、当事者以外の者とのパートナーシップがないこと
- 近親者でないこと(養子縁組を解消した場合は宣誓可能) ※以上の要件を満たしていることが必要です。
-
必要書類
- パートナーシップ宣誓書(様式第1号)
- 現住所を確認できるもの(住民票の写し、マイナンバーカード、運転免許証等の官公署が発行した証明書)
- 独身であることを証明する書類(戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、在留カード、官公署が発行した免許証等) ※上記以外に市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
-
宣誓手続きの流れ
-
事前連絡(男女共同参画課)
-
宣誓書及び必要書類提出(対面)
-
宣誓完了
-
パートナーシップ宣誓証明書またはパートナーシップ宣誓証明カードの交付申請
-
宣誓証明書・証明カードの受領
-
行政書士法人畠山事務所は、
お二人が安心して暮らせるお手伝いをいたします(*^-^*)
これらの作成に携わることで、法律による保護を組み立てていき、
法的保護の無いカップルや親子を守る手助けができれば幸いです。
報酬額及びお支払方法について
報酬額については別途ご案内いたします。
原則、クレジットカードでのお支払いのみとさせていただきます。
クレジットカード以外でのお支払いを希望の場合は、ご相談ください。
