遺言書の種類
遺言は民法で定められた方式にのっとってする必要があります。
定められた方式にそっていない遺言は無効になります。
遺言書は大きく分けて、普通方式と特別方式の2つがあります。普通方式による遺言には3種類あり、特別方式による遺言はごく稀です。
自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
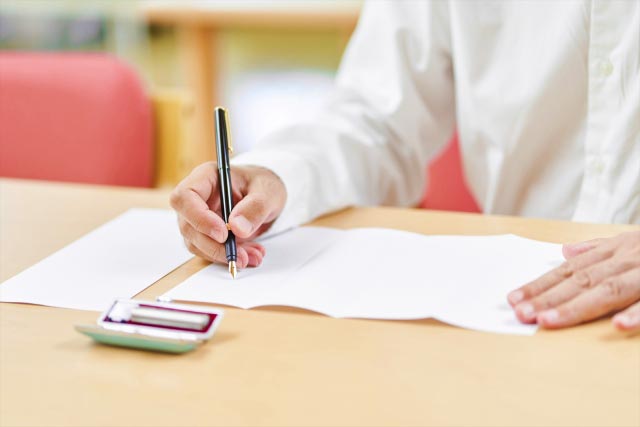
すべての内容を遺言者本人が自筆で書いた遺言です。
ワープロやパソコンあるいは他人に書いてもらった遺言は無効となります。
作成した日付と署名・押印が必ず必要です。 日付は特定できるように書いてください(令和○○年○月○日や○○○○年○月○日など)。
署名・押印も余計な争いを避けるためにも戸籍名・実印が無難です。
自筆証書遺言は費用も必要ありませんし、遺言者以外には秘密にしておけます。一番手軽に作れますが、本当に本人が書いたのか、本人の意思で書いたのかなど、疑いの余地を残すことになります。
字が読みづらかったり、内容が理解できないと無効の原因となります。
また遺言者が亡くなり、相続が開始された後に家庭裁判所での検認の手続きが必要になります。(法務局での保管制度を利用している時は除く)
別紙目録を添付して遺言書を作成する場合、遺言書内に「別紙目録の財産をすべて〇〇に相続させる」と記載すると、財産目録以外に財産があった場合、対象になりませんので注意が必要です。
必要に応じて「全て(別紙目録を含む)を○○に相続させる」など、包括的な表現をおすすめいたします。
公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)

公証人が作成する遺言です。
公証役場へ行き公証人と事前の打ち合わせを行います。(出向くことができない場合は出張もしてくれます。)
このときに本人確認のための書類や説明に必要な書類を持っていきます。
後日、もう一度公証役場へ行き遺言を作成します。遺言作成時は証人2名が必要です。
相続人になる人は証人にはなれません。
公証人からの質問などに対して口頭で説明します。
その内容を公証人が書面にして最後に遺言者、証人2名、公証人が署名・押印して完成です。
原本は、公証役場にて保管されるので偽造や変造される恐れがないため後日家庭裁判所での検認手続きの必要がありません。
秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)

作成はどのような方法でもかまいません。 ワープロやパソコンを使っても良いですし他の人に代筆を頼んでもかまいません。
遺言には署名・押印して封筒に入れます。押印に使用した印鑑と同じものを使い封印します。
作成した遺言書を持って2名以上の証人と一緒に公証役場へ行きます。
公証人と証人の前で、その遺言が自分の遺言であることを述べます。
代筆してもらった場合は、代筆者の住所と氏名も述べなければいけません。
公証人が封筒に提出日と本人が述べたことを記入します。
最後に遺言者、証人公証人が署名・押印して完成です。
遺言者が亡くなり、相続が開始された後に家庭裁判所での検認の手続きが必要になります。
